税務調査に選定される理由
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本は申告納税制度であるため課税庁により税務調査を実施することは「公正な税制」を担保するため必要不可欠となります。 あらためて税務調査とはどのようなもので、その選定理由や流れなどについて触れてみましょう。 【目次】 ◆ 税務調査とは・・・ ◆ 選定理
2023年3月31日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本は申告納税制度であるため課税庁により税務調査を実施することは「公正な税制」を担保するため必要不可欠となります。 あらためて税務調査とはどのようなもので、その選定理由や流れなどについて触れてみましょう。 【目次】 ◆ 税務調査とは・・・ ◆ 選定理
2023年3月31日
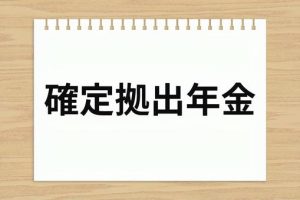
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 最近「新しい資本主義」、「資産所得倍増計画」といったフレーズがメディアによく登場します。 それらを実現するため政府は国民に投資を推奨しています。 そこで「iDeCo」とはどういうものか見ていきましょう。 【目次】 ◆ 「iDeCo」の特徴 ◆
2023年3月30日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 仕事をしていて「執行役員」といった肩書を目にすることも珍しくありません。 近年、取締役会の意思決定の迅速化と取締役の過大な責任の回避のため、取締役の数を絞る傾向があることから、取締役ではない役員待遇の幹部クラス従業員に執行役員の肩書を与えているケースがあります。 取締役
2023年3月29日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 最近話題になることも多いNISAですが、どのようなものか確認したいと思います。 NISAの正式名称は「少額投資非課税制度」といい、銀行や証券会社に専用のNISA口座を開設し、投資で儲かった利益に対して税金を非課税にするといった制度です。 iDeCoとセットで紹介されることもありますが、全く異な
2023年3月28日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 業績が予測よりも好調な時に、従業員に対して決算賞与の支給を検討する会社も多くあるかと思います。 決算間近で臨時賞与の支給を決定した場合、計算や支給手続きなどが間に合わず翌期へ振込等がズレ込んでしまうこともあります。 このようなケースなどでは「未払賞与」として今期の損金に含めるにあたっては気をつける
2023年3月27日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「士業の実力差」とはどういったところに現れるでしょうか。 お客様が初見でそれを正確に見抜くことは難しいことかもしれません。 人と人ですから相性もありますし、表層的な部分だけでは何ごとも本質を見抜くのは難しいかと思います。 我々がお仕事をしていくうえで最も大切なことは、条文や判例等を理解し
2023年3月23日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本の相続税は世界の中で比較するとどの程度なのでしょうか。 日本ではどんなお金持ちでも相続を3度繰り返せばほぼ無くなってしまう、とも言われています。 実際のところはどうなのでしょうか。 検討してみましょう! 【目次】 ◆ 日本の相続税率の変遷 ◆ 世界主要国
2023年3月22日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 相続した親の家などは相続人が住むアテがなければ賃貸するか、売却するかしなければ多くは空き家になってしまいます。 人口が増加し続ける世の中では不動産は資産として十分に魅力があり活用できる資産と言えたのでしょうが、人口が減り続けることが明確な現在では必ずしも資産とはいえません。 そこで売却を検討する際に問
2023年3月20日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税金には各種のペナルティ制度があります。申告しなかったり、期限を守らなかったり、内容が誤っていた場合などに課せられます。 どういったものがあるか見ていきましょう! 【目次】 ◆ 加算税の種類 ◆ 賦課されるケース ◆ おわりに ◆ 加算税の種類 加算税は、「申告納
2023年3月17日

札幌のAimパートナーズ総合会計事務所です。 最近では社会のグローバル化にともなって富裕層にしろ企業にしろ、海外を使った課税逃れが増えています。 海外に移住することも珍しくなくなった昨今、海外を使った課税逃れをご紹介します。 【目次】 ◆ タックスヘイブンとは ◆ 課税逃れ、資産隠しの事例 ◆ おわりに ◆ タックスヘイブンとは タッ
2023年3月16日