金庫番でも仕訳屋でもない
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 経理の仕事は金庫番でも仕訳屋でもありません。 まれに経営者でさえそう思っている方もおりますが、間違っています。 おそらくそのような業務はそれこそDXによりAI等が代替して対応するようになるでしょう。 これから仕事に取り組むうえで「AI等に代替できない仕事をしていかなければならない」という意識を持つことも
2025年6月9日
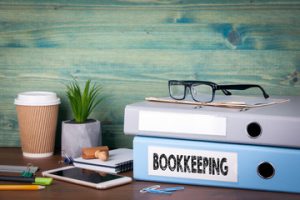
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 経理の仕事は金庫番でも仕訳屋でもありません。 まれに経営者でさえそう思っている方もおりますが、間違っています。 おそらくそのような業務はそれこそDXによりAI等が代替して対応するようになるでしょう。 これから仕事に取り組むうえで「AI等に代替できない仕事をしていかなければならない」という意識を持つことも
2025年6月9日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税理士や社労士試験等国家資格である以上、なかなかに難しい試験かと思います。 私も受験時代は毎日1日10時間くらい勉強し、知識を詰め込み何とか試験に通ることができました。 そこまで苦労して試験に合格したのだから、実務に必要な知識は十分に持っているものと思い込んでいました。 しかし実際に実務の世界に放り込ま
2025年6月6日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 ワーク(仕事)とライフ(人生)のバランスを取ることの重要性が企業でも注目されています。 大切なことだと思います。 しかし、人生の中でワークとライフのバランスが崩れるほどに仕事に没頭する時期も必要だと思います。 「寝食を忘れる」 「我を忘れる」 ほどに仕事に没頭したという経験が「新しい自分」を
2025年6月5日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 会社の運営やルールに関して、現状がベストの方法であるということはあまりなく、必ず改善、修正すべき点があるのではないでしょうか。 悪しき習慣を何年も引きずっているケースも多いのではないでしょうか。 そんなとき、過去のやり方がおかしいと思えば、それを踏襲せずに自分の正しいと思うやり方に変えていけばいいと思います。
2025年6月4日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 若くして大きなことを成し遂げた若者が世界的に増えてきた気がします。 同じ年代の人が成功者としてメディアに取り上げられることもよくあります。 身近なところにも成功した人やお金持ちがいます。 さらにもっと身近な友人、知人が自分よりも収入が断然多かったり、良い暮らしや良いモノを持っていたりする
2025年6月3日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 当然ながら我々の業務は企業の経理部と密接に関連しています。 経理部は会社によっては業務量が非常に多く、大変な部署です。 しかし経理部が発信する情報をもとに各利害関係者が重大な意思決定を行い、それによって経営者、会社、社会が変わっていくことが多くあります。 こんなやりがいのあってすばらしい業務は他に類をみ
2025年6月2日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 部下の育成に関し「フィードバック」はとても重要だと思います。 今では当たり前のように使われるようになったフィードバックという言葉ですが、そもそもは軍事用語だそうです。 「このままいくと目標地点からどれくらいズレて砲弾が着弾しそうか、射手に情報を戻すこと」を指すそうです。 ビジネスに置き換えると「このまま
2025年5月30日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 毎日使っている日本語ですが、「感じよく使う」ためには相当の技術が必要だと思います。 「ありがとう」 「さようなら」 「すみません」 といった基本的なあいさつですら時と場合によっては失礼な言葉にもなりえます。 上記の言葉も、 「お忙しいのにありがとうございます。」 「失礼いたします
2025年5月29日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 労働新聞の記事を拝見して参考までに・・・・。 ジャパネットさんではパートを含む従業員5,000人を対象に「不妊治療サポート休職制度」を導入しています。 女性従業員に最大で1年間の休職を認める一方、男性も1か月まで取得可能です。 利用回数は在職中に一回のみとし、分割取得は認めない。 女性は43歳まで
2025年5月28日

Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「良い会社」の定義はいろいろあるかと思います。 社会への貢献という側面からみたとき下記の点は重要なポイントになるものと考えます。 ・ 社員の子供の数が多い ・ 黒字経営であり納税責任を果たしている ・ 社員の給与は適正に支払われている ・ 社員のモチベーション、働きがいは高い
2025年5月27日